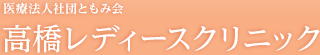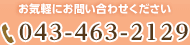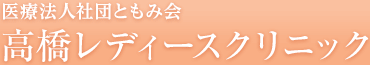新着情報News
経膣超音波検査の費用について
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用されることに伴い、患者様の費用負担が軽減される形となりました。
これまで当院では、保険適用の回数制限を超えた経膣超音波検査について、既定の金額(税込5,247円)ではなく保険適用時の自己負担額(1,430円)のみいただいておりましたが、4月以降は以下のように変更させていただきます。
経膣超音波検査の保険適用制限
自然周期:月1回まで
排卵誘発周期:月3回まで
※治療内容により保険適用の回数が異なります
上記を超える経膣超音波検査は保険適用されず、税込 3,300 円を自費負担とします。
凍結胚を保管中の方へ
現在判明している情報によると、凍結胚の延長代が保険適用されるためには
・凍結日から起算して1年が経過している
・凍結日から起算して3年を経過していない
・現在妊娠中ではない
などの条件があるようです。
このため、当院の従来の延長手続きに関して、保管期限の3か月前から期限までに申請していただくようになっていましたが、「凍結日から起算して1年が経過している」の条件に沿うよう、延長手続きの時期を以下のように変更しました。
変更前
➡保管期限の3か月前から期限までに延長申請
変更後
➡保管期限から起算して1か月間を更新期間とし、更新期間内に延長申請
詳細は「凍結胚の保管に関する規則」をご参照ください。
なお、現在までの情報だけでは、令和3年3月31日までに凍結した場合や、もともとの保管期限が令和4年3月31日以前までの場合、令和4年4月1日以降に延長手続きを行っても保険適用とはならない可能性がありますのでご了承ください。